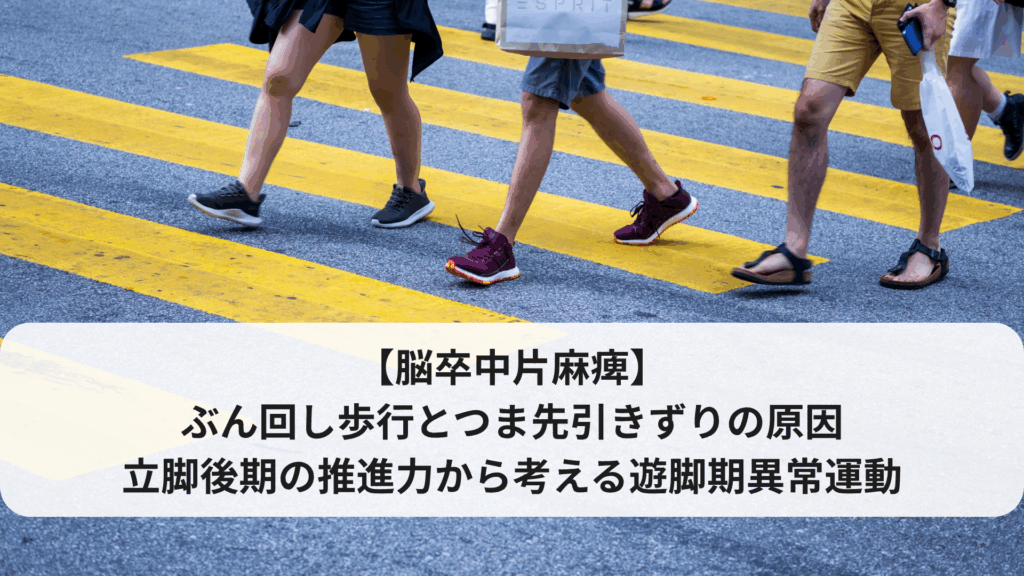
Contents
はじめに
脳卒中片麻痺患者の歩行では、麻痺側下肢の遊脚期に特徴的な異常パターンを観察することが多くあります。股関節を外転・外旋させながら振り出す「ぶん回し歩行(circumduction)」や、足尖が床面を擦る「つま先引きずり」です。
これらの問題に対して、足関節背屈筋の筋力強化や股関節屈曲の促通、装具療法などの介入を行うことは一般的です。しかし、遊脚期の異常運動に対して遊脚期そのものにアプローチすることが、本質的な解決につながっているでしょうか。
近年の研究から興味深い知見が得られています。遊脚期の異常運動は、実は立脚後期の推進力(propulsion)生成の問題によって引き起こされている可能性が高いということです。
Neptune et al.(2001)は、足関節底屈筋が立脚後期に生成する推進力が、身体重心の前方移動だけでなく、遊脚期の開始にも重要な役割を果たすことを示しました。つまり、「足が前に出ない」問題の本質は、「後ろ足で蹴れていない」ことにある可能性が高いのです。
本稿では、立脚後期の推進力と遊脚期運動学の関係について、最近の研究知見を整理し、臨床評価・介入への示唆を考えていきます。
具体的には、以下の3つの観点から検討します:
- 推進力の「量」の問題(立脚後期の異常な制動力と遊脚期異常)
- 推進力の「タイミング」の問題(ピーク発生時期のズレ)
- 遊脚期における代償戦略の多様性
推進力の「量」の問題:Late Braking Forcesと遊脚期異常
立脚後期の異常な制動力
Dean et al.(2020)は、29名の慢性期脳卒中患者を対象に、立脚後期の推進力と遊脚期キネマティクスの関係を詳細に分析しました。この研究で最も注目すべき発見は、一部の脳卒中患者が立脚後期に異常な制動力(late braking forces)を示すことでした。
通常、健常者であれば立脚後期(pre-swing)には強い前方への推進力を生成します。しかし、この研究の対象者の一部は、推進力を生成すべき時期に逆に後方への制動力を生成していたのです。
“A subset of the stroke survivors exhibited unusual braking forces late in the paretic stance phase, when strong propulsion typically occurs among uninjured controls.”
(一部の脳卒中患者は、健常者であれば通常強い推進力が生じる麻痺側立脚後期に、異常な制動力を示した)
統計解析の結果、このlate braking impulseの大きさが、遊脚期の異常運動と有意に関連していることが明らかになりました:
- Late braking impulseが大きい → 遊脚期の膝屈曲角度が減少(p=0.039)
- Late braking impulseが大きい → 分回し歩行(circumduction)が増加(p=0.023)
興味深いことに、推進力の「量」(propulsive impulse)そのものよりも、この異常な制動力の方が遊脚期運動との関連が強かったのです。つまり、「推進力が弱い」だけでなく、「推進すべきタイミングで制動している」ことが、より大きな問題である可能性があります。
下肢伸展角度(Trailing Limb Angle)の重要性
では、なぜこのような異常な制動力が生じるのでしょうか。Peterson et al.(2010)は、51名の脳卒中患者と21名の健常者を対象とした階層的回帰分析により、推進力生成の予測因子を検討しました。
結果は明確でした。Trailing limb angle(TLA)、すなわち立脚後期の下肢伸展角度が、推進力の最も重要な予測因子だったのです:
- 麻痺側TLA: β=0.86 (p<0.001)
- 非麻痺側TLA: β=1.28 (p<0.001)
- 健常者TLA: β=0.94-1.32 (すべてp<0.001)
TLAは、大転子と第5中足骨頭を結ぶ線と鉛直線のなす角度として定義されます。この角度が大きいほど、つまり立脚後期に下肢が十分に後方へ伸展しているほど、推進力生成が大きくなるということです。
逆に言えば、十分な下肢伸展が得られない場合、足部が身体重心より十分に後方に位置せず、伸展筋力が前方への推進力ではなく制動力として働いてしまう可能性があります。これが、Dean et al.が観察したlate braking forcesの発生メカニズムの一つと考えられます。
股関節屈曲モーメントの負の影響
Peterson et al.はもう一つ重要な発見をしています。股関節屈曲モーメントが推進力と負の関連を示すことです(β=-0.038 to -0.065)。
これは、立脚後期に股関節屈曲筋が過剰に活動すると、推進力生成を妨げる可能性を示唆します。立脚後期の早すぎる股関節屈曲活動が、下肢の十分な後方伸展を妨げ、結果として推進力低下につながっている可能性があります。
推進力の「タイミング」の問題:早すぎるピーク発生
推進力生成の問題は「量」だけではありません。Alam et al.(2022)は、推進力関連変数の時間的タイミングに着目した研究を行いました。これは、推進力研究において比較的新しい視点です。
ピーク推進力の早期化
13名の脳卒中患者と9名の健常者を比較した結果、麻痺側下肢では推進力のピークが有意に早期に出現することが明らかになりました:
- Peak AGRF(前方床反力)のタイミング: 麻痺側は健常者より約9%早期(p<0.001, effect size g=2.21)
- Peak ankle powerのタイミング: 麻痺側は非麻痺側より約3.3%早期(p=0.032)、健常者より約3.4%早期(p=0.024)
- Peak ankle momentのタイミング: 麻痺側は健常者より約3.0%早期(p=0.018)
ここで重要なのは、この「早期」の意味です。この研究ではtoe-off(つま先離地)からの時間で測定しています。パーセンテージが大きいほど、toe-offよりも早い時期にピークが出現していることを意味します。
つまり、麻痺側では本来toe-offの直前に最大になるべき推進力が、立脚期の比較的早い段階でピークに達し、その後は減衰してしまっているのです。理想的には、推進力は立脚後期に向けて徐々に増加し、toe-offの直前で最大となるべきですが、麻痺側ではこのパターンが崩れています。
タイミング異常の臨床的意義
健常者を対象とした研究(Kuhman & Hurt, 2019)では、歩行速度が変化しても推進力のピークタイミングは比較的一定に保たれることが示されています。これは、推進力のタイミングが神経系によって厳密に制御されていることを示唆する重要な知見です。
Alam et al.は、この早期ピーク発生のメカニズムとして以下を考察しています:
- 底屈筋の筋力低下・萎縮により、筋が持続的・急速な収縮を維持できず、立脚後期まで推進力を高め続けることができない
- 不適切な足部位置により、両脚支持期に効率的な推進力生成の準備ができていない
- 股関節伸展不足により、適切なタイミングで最大推進力を生成できる身体配置にならない
“The earlier onset of peak AGRF, peak ankle power, and peak ankle moment may be an important, under-studied biomechanical factor underlying stroke gait impairments.”
(ピークAGRF、ピーク足関節パワー、ピーク足関節モーメントの早期出現は、脳卒中歩行障害の根底にある、十分に研究されていない重要なバイオメカニクス的因子である可能性がある)
なぜタイミングが重要なのか
適切なタイミングでの推進力生成は、Kuo & Donelan(2010)が指摘するように、代謝効率の最適化と歩行の安定性に寄与します。
具体的には:
- toe-off直前の最大推進力は、遊脚肢への力学的エネルギーの効率的な伝達を可能にする
- 早すぎる推進力ピークは、toe-off時に十分な力学的エネルギーが残っておらず、遊脚期の開始を困難にする
- タイミングのずれは、過剰な股関節トルクによる代償を必要とし、エネルギー効率を低下させる
この「量は足りているがタイミングがずれている」という視点は、臨床評価においても重要です。単純に「推進力が弱い」と評価するだけでなく、いつピークが出現しているかを観察することで、介入ポイントがより明確になる可能性があります。
遊脚期における代償戦略の多様性
立脚後期の推進力生成の問題が遊脚期異常を引き起こすことは明らかになりましたが、では患者はこの問題に対してどのような戦略で対応しているのでしょうか。
Roche et al.(2015)は、60名の慢性期脳卒中患者を対象に、遊脚期の股関節屈曲角度と足関節背屈角度の関係を詳細に分析しました。この研究の重要な発見は、遊脚期の運動戦略には2つの異なるパターンが存在することです。
Distal Strategy vs Proximal Strategy
遊脚期の股関節屈曲角度と足関節背屈角度の間には有意な負の相関が認められました(r=-0.26, p=0.04)。つまり、足関節背屈が大きい患者ほど股関節屈曲は小さく、逆に背屈が小さい患者ほど股関節屈曲が大きいという関係が存在します。
“There was a significant negative correlation between peak ankle dorsiflexion and peak hip flexion during swing (R=-0.26; p=0.04).”
(遊脚期の股関節屈曲角度と足関節背屈角度の間には有意な負の相関が認められた)
この結果は、脳卒中患者が遊脚期のトゥクリアランス確保のために2つの異なる戦略を使い分けていることを示唆します:
1. Distal Strategy(遠位戦略)
- 十分な足関節背屈が可能な場合に選択される
- 股関節屈曲を過度に増加させる必要がない
- より健常者に近い運動パターン
2. Proximal Strategy(近位戦略)
- 足関節背屈が不十分な場合に選択される
- 股関節屈曲の増大によって代償
- トゥクリアランスを確保するための代償戦略
背屈不足のあるサブグループ(22名、平均ピーク背屈角度-7.6°)では、toe-offから最大背屈時までの足関節角度変化と股関節角度変化の間に有意な負の相関(r=-0.43, p=0.04)が認められた一方、背屈が保たれているサブグループ(38名、平均ピーク背屈角度+6.7°)ではこの相関は認められませんでした(r=-0.16, p=0.31)。
これは、背屈不足がある患者ほど、股関節屈曲による代償戦略を積極的に使用していることを意味します。
臨床的観察との一致
この2つの戦略の存在は、臨床場面でよく観察される「シンキネジア(連合反応)」とも関連している可能性があります。脳卒中患者では、随意的な足関節背屈を試みると、不随意的に股関節屈曲が生じるcoordination synkinesiaが高頻度で観察されます。
静的な臨床評価場面でこのシンキネジアを示す患者では:
- 十分な背屈ができない場合、同時に股関節屈曲を動員する
- 十分な背屈ができる場合、股関節屈曲筋の動員は不要
この静的評価で観察される現象が、歩行中の動的な運動戦略としても表れている可能性があります。つまり、遊脚期の股関節-足関節の協調パターンは、神経学的な結合によって規定されているのかもしれません。
筋力と運動学の乖離
Roche et al.は、股関節屈筋力と足関節背屈筋力の間に有意な正の相関(r=0.44, p=0.0003)があることも報告しています。
しかし重要なのは、筋力が高いからといって必ずしも正常な関節運動が得られるわけではないという点です。高いMRCスコアを示しても、遊脚期の股関節屈曲角度や足関節背屈角度は必ずしも正常値に達しない患者が多数存在しました:
- 股関節屈筋力と遊脚期の最大股関節屈曲角度の間に相関なし(r=-0.0001, p=0.99)
- 足関節背屈筋力と遊脚期の最大背屈角度の間に相関なし(r=0.09, p=0.46)
これは、筋力だけでなく、運動制御の問題やタイミングの問題が遊脚期運動学に影響を与えていることを示唆します。MMTで4や5を示す患者であっても、歩行時には異なる問題が生じている可能性があるということです。
臨床への示唆
これまでの知見を踏まえて、臨床評価と介入への示唆を考えていきます。
長距離歩行能力への影響
Awad et al.(2015)は、44名の慢性期脳卒中患者を対象に、バイオメカニクス変数と6分間歩行距離(6MWT)の関係を検討しました。
段階的重回帰分析の結果、麻痺側の推進力(Propulsion)とTrailing Limb Angle(TLA)の2つの変数のみが、6MWT距離の65.5%の分散を説明しました(R²=0.655, p<0.001):
- Propulsion: β=0.339 (p=0.031)
- TLA: β=0.564 (p=0.005)
一方、遊脚期変数(膝屈曲、足関節背屈)や対称性変数(ステップ長対称性、遊脚時間対称性)は、独立した予測因子とはなりませんでした。
この結果は、長距離歩行能力を改善するためには、立脚後期の推進力生成能力が最も重要なターゲットであることを示唆します。脳卒中患者の多くが「長い距離を歩けない」ことを主訴としますが、その改善には立脚後期へのアプローチが不可欠なのです。
評価のポイント
これらの研究結果から、以下の評価ポイントが重要と考えられます:
1. Trailing Limb Angleの測定
TLAは、立脚後期の下肢伸展角度を示す指標です。大転子と第5中足骨頭を結ぶ線と鉛直線のなす角度として定義され、臨床現場でも比較的容易に測定可能です。
Awad et al.は、TLAが推進力の代替指標として有用であることを示しています。三次元動作分析装置がない環境でも、ビデオ撮影とマーカーを用いて評価できる可能性があります。
2. 推進力のタイミング観察
単に「推進力が弱い」だけでなく、いつピークが出現しているかを観察することが重要です。立脚期の早期にピークが出現し、toe-off時には減衰している場合、タイミングの問題が存在する可能性があります。
3. 遊脚期戦略の識別
患者がDistal StrategyとProximal Strategyのどちらを使用しているかを評価することで、介入の方向性が明確になります:
- 背屈が不十分で股関節屈曲が過剰 → 近位戦略への依存
- 背屈が十分で股関節屈曲が適切 → 遠位戦略の使用
介入への示唆
1. 立脚後期へのアプローチの重要性
遊脚期の異常運動に対して、遊脚期そのものにアプローチするだけでは不十分かもしれません。立脚後期の推進力生成能力を改善することが、遊脚期運動学の改善にもつながる可能性があります。
具体的には:
- 足関節底屈筋の筋力強化(特に持久力)
- 立脚後期の股関節伸展可動域の確保
- 立脚後期の股関節屈筋の早期活動抑制
- TLAを意識した歩行練習
2. 量とタイミング両面へのアプローチ
推進力の「量」だけでなく「タイミング」も重要です。立脚期を通じて推進力を漸増させ、toe-off直前に最大となるようなタイミング制御が必要です。
トレッドミルを用いた高強度歩行練習は、このタイミング制御の学習に有効かもしれません。
3. 個別化された戦略
患者がどの戦略を使用しているかによって、介入の優先順位が変わります:
- 近位戦略依存の患者: まず立脚後期の推進力改善、それに伴う遠位戦略への移行を目指す
- 遠位戦略使用の患者: 現在の戦略を維持しつつ、さらなる効率化を図る
FAQ(よくある質問)
Q1. 遊脚期の異常運動に対して、なぜ立脚後期にアプローチする必要があるのですか?
A. 遊脚期の膝屈曲低下や分回し歩行は、立脚後期の推進力不足が根本原因である可能性が高いためです。Dean et al.(2020)は、立脚後期の異常な制動力(late braking forces)が遊脚期異常と有意に関連することを示しました(膝屈曲:p=0.039、分回し:p=0.023)。推進力が不足すると遊脚期の開始が困難になり、代償的な運動パターンが生じます。
Q2. Trailing Limb Angle(TLA)とは何ですか?臨床でどう活用できますか?
A. TLAは立脚後期の下肢伸展角度を示す指標で、大転子と第5中足骨頭を結ぶ線と鉛直線のなす角度です。Peterson et al.(2010)によれば、TLAは推進力の最も重要な予測因子(β=0.86-1.28, p<0.001)です。三次元動作分析装置がなくても、ビデオ撮影とマーカーで測定可能なため、推進力の代替指標として臨床で活用できます。
Q3. Distal StrategyとProximal Strategyの違いは何ですか?
A. Roche et al.(2015)が示した2つの遊脚期戦略です。Distal Strategy(遠位戦略)は、十分な足関節背屈でトゥクリアランスを確保する健常者に近いパターン。Proximal Strategy(近位戦略)は、背屈不足を股関節屈曲増大で代償するパターンです。背屈不足群では股関節-足関節の角度変化に負の相関(r=-0.43, p=0.04)が認められました。
Q4. 推進力のタイミング異常とは具体的にどういうことですか?
A. Alam et al.(2022)によれば、麻痺側では推進力のピークがtoe-offより約9%早期に出現します(p<0.001, effect size=2.21)。本来toe-off直前に最大となるべき推進力が、立脚期の早い段階でピークに達し減衰してしまうため、遊脚期開始時に十分なエネルギーが残っていない状態です。量だけでなくタイミングも評価・介入のターゲットとなります。
Q5. MMTで高スコアでも歩行時の関節角度が改善しないのはなぜですか?
A. Roche et al.(2015)は、股関節屈筋力と遊脚期の最大股関節屈曲角度に相関がないこと(r=-0.0001, p=0.99)、足関節背屈筋力と遊脚期の最大背屈角度にも相関がないこと(r=0.09, p=0.46)を示しました。これは筋力だけでなく、運動制御の問題、タイミングの問題、神経学的結合などが遊脚期運動学に影響するためです。静的評価と動的評価を組み合わせる必要があります。
Q6. 立脚後期へのアプローチで長距離歩行能力は改善しますか?
A. はい、改善する可能性が高いです。Awad et al.(2015)は、麻痺側の推進力とTLAの2変数のみが6分間歩行距離の65.5%を説明することを示しました(R²=0.655, p<0.001)。遊脚期変数や対称性変数は独立した予測因子とならず、立脚後期の推進力生成能力が長距離歩行の最も重要な決定因子であることが明らかになっています。
Q7. 立脚後期へのアプローチの具体例を教えてください
A. 以下のような介入が考えられます:(1)足関節底屈筋の筋力強化、特に持久的収縮能力の向上、(2)立脚後期の股関節伸展可動域の確保、(3)立脚後期の股関節屈筋の早期活動抑制、(4)TLAを意識した歩行練習、(5)トレッドミルを用いた高強度歩行練習によるタイミング制御の学習。患者がどの戦略(Distal/Proximal)を使用しているかによって優先順位を個別化します。
Q8. シンキネジアと遊脚期戦略の関係について教えてください
A. 脳卒中患者では随意的な足関節背屈時に不随意的な股関節屈曲が生じるcoordination synkinesiaがよく観察されます。この静的評価で観察される現象が、歩行中の動的戦略としても表れている可能性があります。背屈不足の患者では股関節屈曲で代償(Proximal Strategy)、背屈が十分な患者では股関節過剰屈曲は不要(Distal Strategy)という使い分けが、神経学的な結合によって規定されているかもしれません。
まとめ
本稿では、脳卒中片麻痺患者の遊脚期異常運動が、実は立脚後期の推進力生成の問題に起因している可能性を、複数の研究知見から検討しました。
主要なポイントをまとめます:
- 推進力の「量」の問題: 立脚後期の異常な制動力(late braking forces)が遊脚期の膝屈曲低下や分回し歩行と関連する。Trailing Limb Angleが推進力の最も重要な予測因子である。
- 推進力の「タイミング」の問題: 麻痺側では推進力のピークが早期に出現し、toe-off時には減衰している。このタイミング異常も遊脚期運動に影響する可能性がある。
- 遊脚期戦略の多様性: 患者は背屈能力に応じて、Distal Strategy(遠位戦略)とProximal Strategy(近位戦略)を使い分けている。筋力と運動学は必ずしも一致しない。
- 長距離歩行への影響: 推進力とTLAが長距離歩行能力の最も重要な決定因子であり、臨床的に重要なターゲットである。
「足が前に出ない」という問題に対して、私たちはつい遊脚期そのものに注目してしまいがちです。しかし、その根本原因は立脚後期にあるのかもしれません。
今後の臨床実践では、立脚後期の推進力生成能力を評価し、量とタイミングの両面から改善を図ることが、遊脚期異常運動の本質的な解決につながる可能性があります。
TLAのような臨床現場で測定可能な指標を活用しながら、エビデンスに基づいた評価と介入を実践していきたいと思います。
参考文献
- Neptune RR, Kautz SA, Zajac FE. Contributions of the individual ankle plantar flexors to support, forward progression and swing initiation during walking. J Biomech. 2001;34(11):1387-1398. https://doi.org/10.1016/s0021-9290(01)00105-1
- Dean JC, Bowden MG, Kelly AL. Altered post-stroke propulsion is related to paretic swing phase kinematics. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2020;72:24-30. https://doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2019.11.024
- Peterson CL, Cheng J, Kautz SA, Neptune RR. Leg extension is an important predictor of paretic leg propulsion in hemiparetic walking. Gait Posture. 2010;32(4):451-456. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2010.06.014
- Alam M, Varas-Diaz G, Tirone S, Kautz SA, Enterline C, Hurt CP. Timing of propulsion-related biomechanical variables is impaired in individuals post-stroke. Gait Posture. 2022;96:58-63. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2022.05.022
- Kuhman D, Hurt CP. Lower propulsion does not modulate propulsion timing variability in human walking. Hum Mov Sci. 2019;67:102524. https://doi.org/10.1016/j.humov.2019.102524
- Kuo AD, Donelan JM. Dynamic principles of gait and their clinical implications. Phys Ther. 2010;90(2):157-174. https://doi.org/10.2522/ptj.20090034
- Roche N, Bonnyaud C, Geiger M, Bussel B, Bensmail D. Relationship between hip flexion and ankle dorsiflexion during swing phase in chronic stroke patients. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2015;30(3):219-225. https://doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2015.02.001
- Awad LN, Binder-Macleod SA, Pohlig RT, Reisman DS. Paretic propulsion and trailing limb angle are key determinants of long-distance walking function after stroke. Neurorehabil Neural Repair. 2015;29(6):499-508. https://doi.org/10.1177/1545968314554625
執筆者情報
三原拓(みはら たく)
ニューロスタジオ千葉 理学療法士
主な研究業績
2016,18年 活動分析研究大会 口述発表 応用歩行セクション座長
2019年 論文発表 ボバースジャーナル42巻第2号 『床からの立ち上がり動作の効率性向上に向けた臨床推論』
2022年. 書籍分担執筆 症例動画から学ぶ臨床歩行分析~観察に基づく正常と異常の評価法
p.148〜p.155 株式会社ヒューマン・プレス
その他経歴
2016年 ボバース上級講習会 修了
2024年 自費リハビリ施設 脳卒中リハビリパートナーズhaRe;Az施設長に就任
2025年 株式会社i.L入職 NEUROスタジオ千葉の立ち上げ
現在の活動
ニューロスタジオ千葉 施設長
脳卒中患者様への専門的リハビリ提供
療法士向け教育・指導活動
千葉ハンドリングセミナー共同代表

