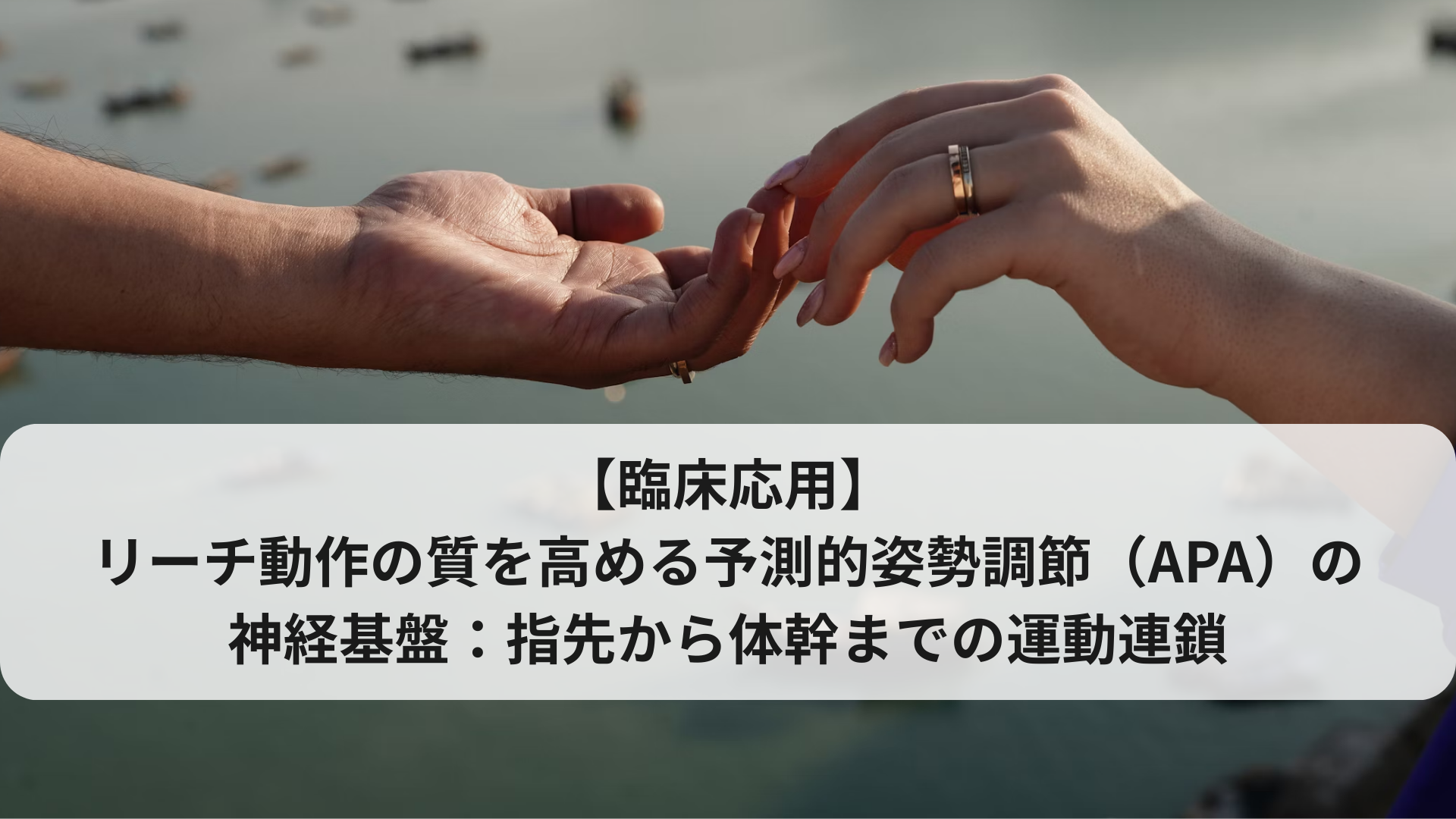
Contents
1. はじめに:「運動連鎖」の視点でリーチ動作を捉え直す
理学療法において、対象者の生活機能を高める上で「リーチ動作」、すなわち腕を伸ばして物に手を届かせる能力の再建は、最も重要な目標の一つです。食事、更衣、整容といった日常生活動作の多くは、このリーチ動作が基盤となっています。臨床では、主動作筋の筋力や関節可動域といった要素に注目しがちですが、質の高い効率的なリーチ動作は、単なる腕の動きだけで完結するものではありません。
実は、腕が動き出すよりもわずかに早く、私たちの身体は運動によって生じるであろう重心の移動や姿勢の乱れを「予測」し、それを打ち消すための「準備」を始めています。この運動に先行する一連の準備こそが予測的姿勢調節(Anticipatory Postural Adjustments: APA)と呼ばれる神経制御機構です 。APAは、中枢神経系が運動指令と並行して、あるいはそれよりも先に姿勢制御のための指令を送り出す、精緻なフィードフォワード(予測的)制御の一環です。運動という行為が、実は「動き」そのものと、それを支える「姿勢」という、二つの要素の協調によって成り立っていることを示唆しています 3。
本稿では、このAPAを、「指先の微細な動きを起点とし、上肢の安定化を経て、体幹や下肢の動的バランス維持へと至る一連の『運動連鎖』の制御」という新たな視点で捉え直します。なぜ指を動かすだけで肩や肘が備え、腕を振るだけで足腰が反応するのか。この見えざる連鎖の神経基盤を科学的エビデンスに基づき解き明かし、脳卒中リハビリテーションをはじめとした臨床応用への可能性を探ります。
2. 連鎖の起点:指先の動きが上肢全体の安定化を要求する
リーチ動作を構成する運動連鎖は、どこから始まるのでしょうか。驚くべきことに、その起点は非常に末梢の、ごくわずかな動きにさえ見出すことができます。中枢神経系は、局所的な運動が上肢全体に及ぼす力学的な影響を正確に予測し、動作に先立って腕全体を安定させる制御、すなわち「分節的APA」を実行します。
指先の微細な動きが上肢全体の「固定鎖」を作る
日常でペンを持ったり、ボタンを押したりするような、ごく軽微な指の動きでさえ、上肢全体の予測的な準備活動を引き起こします。Bolzoniら (2012) が引用する研究では、この現象が明確に示されています。
“Indeed, we have recently shown (Caronni and Cavallari 2009a) that
even a gentle index finger flexion is preceded by a complex fixation chain, which distributes to several upper limb muscles”.
(和訳: 事実、我々は最近、穏やかな人差し指の屈曲運動でさえ、それに先立って上肢の複数の筋に分配される、複雑な固定鎖(fixation chain)が生じることを示した。)
つまり、指をわずかに動かすという指令が出されると同時に、脳は腕全体を一つの機能的なユニット、いわば「固定鎖」として扱い、手関節、肘、肩に至るまでの筋活動を事前に調整して、運動の土台を固めているのです。
手関節の運動方向に応じてプログラムされるAPA
この分節的APAのプログラムは、より大きな運動である手関節の動きにおいて、さらに精巧な姿を見せます。Chabranら (1999, 2001) は、被験者が手関節の屈曲・伸展運動を行う際に、肘や肩周囲の筋活動がどのように先行するのかを詳細に分析しました。
その結果、手関節の屈曲時には上腕二頭筋が、伸展時には上腕三頭筋が、それぞれ手関節を動かす主動作筋よりも統計的に有意に早く活動を開始することが明らかになりました 。この筋活動の順序は、運動方向に応じて事前にプログラムされており、再現性が高いものでした 。
なぜこのような特定の順序で筋が活動するのでしょうか。Chabranら (1999) は、単純な力学モデルを用いてその理由を説明しています。
“The model revealed that when a wrist flexion is performed, a flexion torque must be applied to the elbow and shoulder joints in order to maintain the upper limb posture and, on the opposite, an extension torque must be applied to prevent a movement of these joints during a wrist extension”.
(和訳: モデルが明らかにしたのは、手関節の屈曲時には、上肢の姿勢を維持するために肘と肩の関節に屈曲トルクが加えられなければならず、逆に手関節の伸展時には、これらの関節の動きを防ぐために伸展トルクが加えられなければならない、ということである。)
つまり、先行する肘・肩周りの筋活動は、これから起こる手関節の運動が作り出す「関節間相互作用トルク」という物理的な力を打ち消し、指示されていない関節が動いてしまうのを防ぐための、極めて合理的な制御なのです。
「不使用」が運動連鎖プログラムを乱す
この上肢内で統合されたAPAプログラムがいかに重要であるかは、Bolzoniら (2012) のギプス固定研究によって浮き彫りにされました。健常者の手関節と手指をわずか12時間ギプスで固定しただけで、驚くべき変化が見られたのです。
固定を外した直後、指の運動自体(主動作筋である浅指屈筋の活動や指の動きの大きさ・速さ)に変化はなかったにもかかわらず、固定されていなかった肘や肩のAPAパターンが有意に変容しました 。具体的には、上腕二頭筋と三角筋前部の抑制性APAが増強し、上腕三頭筋の促通性APAが減少した結果、指の運動中に生じる肘関節のブレが有意に大きくなりました。
この知見は、脳卒中後の麻痺側上肢に見られる「学習性不使用」を考える上で、極めて重要な示唆を与えます。麻痺によって末端の動きが制限されることが、単にその部分の機能を低下させるだけでなく、上肢全体の運動を制御する神経プログラムそのものを変容させてしまう可能性を示しているのです。
これらの研究から、運動連鎖の起点は、運動部位を局所的に安定させる精巧な分節的APAにあることがわかります。中枢神経系は、たとえ指先を動かすだけであっても、上肢全体を一つのユニットとして捉え、その安定性を予測的に確保しているのです。
3. 連鎖の伝播:上肢の動きが体幹・下肢の反応を惹き起こす
指先の動きから始まった運動連鎖は、上肢の安定化に留まりません。特に立位のように身体全体のバランス維持が求められる状況では、その連鎖は体幹、そして下肢へと瞬時に伝播します。これは、腕を動かすという行為が身体の重心に与える影響を予測し、転倒を防ぐための「全身的APA」と呼ぶべき、より大規模な姿勢制御プログラムです。
腕の動きに先行する、下肢の準備活動
この全身的APAの存在を古典的かつ明確に示したのが、CordoとNashner (1982) の研究です 。彼らは、被験者が立位で腕を素早く前方に振り上げる際に、身体に何が起きるかを筋電図と床反力計で詳細に分析しました。その結果は、運動制御の常識を覆すものでした。
“Consistent with the findings of Pal’tsev and El’ner and Belen’kii et al,
postural reactions preceded focal movements. Following a tone stimulus, gastrocnemius response time was RT = 111 ± 27, with a range of 81-170 ms.”
(和訳: Pal’tsevとEl’ner および Belen’kiiらの知見と一致して、姿勢反応は主運動に先行した。音刺激の後、腓腹筋の反応時間はRT=111±27msであった。)
※本文中ではGastrocnemius(腓腹筋)のデータが示されているが、後の研究ではSoleus(ヒラメ筋)など下腿後面の筋活動として広く知られる。
つまり、腕を動かす主動作筋である三角筋などが活動を開始するよりも約50ミリ秒も早く、身体の後方への転倒を防ぐために下腿後面の筋(腓腹筋やヒラメ筋)が活動を開始していたのです。この先行する下肢の活動により、身体の重心は腕が前方に振り出される前にごくわずかに後方へ移動します。この準備的な重心移動が、腕の運動によって生じる前方への重心移動を相殺し、結果として身体の安定が保たれるのです。
運動方向に応じて最適化されるAPAの「方向特異性」
さらに重要なのは、この全身に及ぶAPAが、あらゆる動きに対して画一的に生じる単純な反応ではないという点です。中枢神経系は、これから行う運動の方向を正確に予測し、それに応じて動員する筋群を巧みに使い分けます。この性質は「方向特異性」として知られています。
AruinとLatash (1995) は、被験者に立位で腕を様々な方向に素早く振らせる実験を行いました 。その結果、APAとして活動する体幹・下肢の筋活動パターンは、腕を振る方向によって劇的に変化することが明らかになりました。
“The proximoaxial muscles demonstrated a pronounced unimodal reciprocal pattern consisting of an increase in the background activity in the muscle’s own range and a slight decrease in the range of its antagonist.”
(和訳: 近位体幹筋は、自身の活動範囲では背景活動の増加、拮抗筋の範囲ではわずかな減少から成る、顕著な単峰性の相反性パターンを示した。)
具体的には、腕を前方に振る際には、身体が後方へ反るのを防ぐために腹直筋などの屈筋群に強いAPAが見られました。逆に腕を後方へ振る際には、前方へ倒れるのを防ぐために脊柱起立筋などの伸筋群に強いAPAが観察されました 。
この方向特異性は、中枢神経系が単に「腕が動く」という事実だけでなく、「どの方向に、どのくらいの勢いで動くのか」までを予測し、それによって生じるであろう力学的な影響(重心移動の方向と大きさ)を相殺するのに最も効率的な筋の組み合わせ(シナジー)を、事前に選択していることを示しています。運動連鎖の伝播は、極めてインテリジェントな予測制御システムによって支えられているのです。
4. 連鎖の司令塔:APAを司る脳内ネットワークとその役割
指先の微細な動きから体幹・下肢に至るまで、状況に応じて精緻に調整される予測的姿勢調節(APA)。この複雑な運動連鎖は、単一の脳部位ではなく、複数の領域が協調して機能する広範な神経ネットワークによって統括されています。いわば、運動を計画し、実行し、調整するための「司令塔」が脳内に存在しているのです。
fMRIが捉えたAPAの神経基盤
近年、fMRI(機能的磁気共鳴画像法)技術の進歩により、APAに関わる脳活動を直接的に可視化することが可能になりました。Smithら (2022) は、APAを伴う下肢運動(非支持下での挙上)と、伴わない運動(支持下での挙上)の脳活動を比較する画期的な研究を行いました。
その結果、APAを伴う運動では、以下の領域で特異的に、あるいはより顕著に強い活動が認められました。
“In comparison with the SLR [Supported Leg Raise], the ULR [Unsupported Leg Raise] was associated with significantly greater activation in the
right premotor/SMA, left primary motor and cingulate cortices, primary somatosensory cortex, supramarginal gyrus/parietal operculum, superior parietal lobule, cerebellar vermis, and bilateral cerebellar hemispheres.”
(和訳: SLR(支持下での下肢挙上)と比較して、ULR(非支持下での下肢挙上)は、右前頭前野/補足運動野、左一次運動野および帯状回皮質、一次体性感覚皮質、縁上回/頭頂弁蓋部、上頭頂小葉、小脳虫部、および両側の小脳半球において、有意に大きな活動を伴っていた。)
この研究は、APAの生成に、補足運動野(SMA)、一次運動野、そして皮質下の大脳基底核や小脳といった領域が中心的なネットワークを形成していることを強く示唆しています。
司令塔を構成する各部位の役割
これらの脳領域は、APAという一つの機能を実現するために、それぞれ異なる役割を担っていると考えられます。複数の研究知見 を統合すると、その役割分担は以下のように推測されます。
- 補足運動野 (SMA) 運動のプランニングやプログラミング、順序付けを担う中心的な領域です。どのような運動連鎖(筋シナジー)を、どのタイミングで開始するかを決定する、まさに司令塔の中核と言えます。Massion (1992) も、SMAを含む内側前頭前野が、運動に先立つ姿勢制御の準備に関与することを示唆しています。
- 大脳基底核・小脳 運動のスケーリング(大きさや力の調整)とタイミングの精密化に関与します。例えば、これから持ち上げる物の重さや、動かす腕の速度といった情報に基づき、APAの出力を適切に変調させる役割を担っていると考えられます 。特に大脳基底核の障害がAPAの異常を引き起こすことは、パーキンソン病の研究などからも知られています。
- 一次運動野 (M1)・一次体性感覚野 (S1) SMAなどで計画された運動プログラムに基づき、実際の筋収縮を引き起こす最終的な指令を出力するのが一次運動野です。また、運動中に身体から送られてくる感覚フィードバック情報を処理するのが一次体性感覚野であり、これにより運動の微調整が行われます。
このように、APAの制御は、SMAが中心となって運動の青写真を描き、大脳基底核と小脳がその設計図を微調整し、一次運動野が実行部隊に指令を出す、という見事な連携プレーによって成り立っているのです。
Massion (1992) が提唱したように、課題に応じて運動と姿勢が並列的に処理されるのか、あるいは階層的に処理されるのかは未だ議論がありますが 、いずれにせよ、これら複数の脳領域が緊密に連携するネットワークこそが、滑らかで効率的な運動連鎖を実現する司令塔であると言えるでしょう。
5. 連鎖の破綻と再建:脳卒中リハビリテーションにおけるAPAへの介入戦略
これまで見てきた科学的知見は、脳卒中後の上肢機能リハビリテーションという臨床現場において、非常に重要な示唆を与えてくれます。主動作筋の回復だけでなく、運動を支える**「予測」のシステム、すなわちAPAの運動連鎖**に着目することで、より効果的なアプローチへの道が拓かれます。
「破綻」の推測:運動障害の根源を再考する
推測ですが、脳卒中患者様に見られるリーチ動作の拙劣さや不安定性は、単に錐体路の損傷による主動作筋の麻痺や筋力低下だけが原因ではない可能性があります。むしろ、その根底には、これまで述べてきた精緻な運動連鎖プログラムの破綻が潜んでいると考えられます。
- 分節的APAの障害: 指先や手関節を動かそうとする際に、先行すべき肘・肩の安定化プログラムが作動しない、あるいはタイミングが遅れる。これにより、運動の土台がぐらつき、代償的な共同運動パターンが出現しやすくなる。
- 全身的APAの障害: 立位でのリーチ動作において、腕の動きに伴う重心移動を予測し、体幹や下肢でバランスを保つプログラムが破綻する。これにより、転倒への恐怖心から動作自体が過剰にゆっくりになったり、リーチ距離が制限されたりする。
特に、補足運動野(SMA)や大脳基底核、あるいはそれらを結ぶ神経ネットワークが損傷を受けた場合、このAPAプログラムの計画・実行そのものが困難になることが予測されます。
「再建」への介入戦略:APAに着目した3つのアプローチ
この「APAの破綻」という仮説に立つと、リーチ動作の質を再建するためには、APAシステムの再学習を促すアプローチが有効であると考えられます。以下に、科学的エビデンスに基づいた具体的な介入戦略を3つ提案します。
1. 支持条件の操作による感覚入力の調整
APAのプログラムは、身体が置かれた支持条件や、そこから得られる感覚情報によって柔軟に変化します。この特性をリハビリに応用します。
SlijperとLatash (2000) の研究は、この点で重要な知見を提供しています。彼らは、被験者が立位で腕を振る際に、外部の支持条件がAPAにどう影響するかを調べました。その結果、壁などに軽く指で触れる「ライトタッチ」だけで、下肢や体幹のAPAが有意に変化し、姿勢の安定性が増すことを見出しました。
“Leg and trunk muscles showed a significant drop in APAs with added finger touch and no further changes when the touch was substituted with hand grasp.”
(和訳: 脚と体幹の筋は、指の接触を加えることでAPAが有意に減少し、その接触を手の握りに変えてもそれ以上の変化は見られなかった。)
これは、ライトタッチによって得られる微細な体性感覚情報が、中枢神経系にとって姿勢を制御するための強力な参照点となり、過剰なAPAを抑制してより効率的な制御を可能にすることを示唆しています。
【臨床応用案】
- 立位でのリーチ練習の初期段階で、非麻痺側の手で壁やテーブルに軽く触れさせながら(ライトタッチ)課題を行う。これにより、APAの要求度を下げ、成功体験を促す。
- 徐々にその支持をなくしていく、あるいはセラピストが麻痺側体幹部に軽く触れるなど、感覚入力を補助しながらAPAシステムの再学習を段階的に促す。
2. 運動パラメータの多様化によるAPAプログラムの般化
APAは、特定の運動に対して最適化された方向特異的なプログラムです。したがって、その再学習には、多様な運動経験が不可欠です。
AruinとLatash (1995) が示したように、腕を前方に振る時と後方に振る時では、APAとして活動する体幹・下肢の筋群は全く異なります。これは、単一方向への反復練習だけでは、あらゆる方向へのリーチに対応できる柔軟なAPAプログラムを再建できないことを意味します。
【臨床応用案】
- リーチ練習において、常に正面の同じ位置にある対象物だけを目標にしない。
- 前方、側方、斜め上方、下方、さらには体幹の回旋を伴う対側へのリーチなど、様々な方向への運動を課題に取り入れる。
- 腕を動かす速度や、対象物の重さ(負荷)を変化させることも、多様な外乱に対応できるAPAのスケーリング能力を再学習させる上で重要である。
3. 準備過程の最適化によるAPAの発現の促通
APAは「予測」に基づく制御であるため、運動前の「準備」の仕方がその質に大きく影響します。
Cuisinierら (2005) は、運動開始の合図の前に設けられる準備時間(予備時間:foreperiod)の長さがAPAに与える影響を調査しました。その結果、立位での腕挙上運動において、700ミリ秒の準備時間が与えられた際に、最も反応時間(この研究ではpremotor time)が短縮し、最適な準備状態が整うことが示されました。
“In the standing condition, the premotor time significantly decreased from FD500 to FD700 … and increased from FD700 to FD900” (和訳: 立位条件では、premotor timeは予備時間500msから700msにかけて有意に減少し、700msから900msにかけて増加した。)
これは、急かされる状況(準備時間が短すぎる)や、待ちくたびれる状況(準備時間が長すぎる)では、最適なAPAプログラムを準備・実行することが難しいことを示唆しています。特に、自己のペースで運動を開始する場合の方が、外部の合図に急に反応する場合よりもAPAの準備をしやすいことも多くの研究で示唆されています。
【臨床応用案】
- リーチ動作を促す際に、急かすような声かけや、予測不能なタイミングでの指示は避ける。
- 「3、2、1、はいどうぞ」のように明確な合図で十分な準備時間を与えるか、あるいは対象者の任意のタイミングで運動を開始させる(自己ペース)。
- このような環境設定が、脳卒中によって処理速度が低下した脳卒中患者のAPAプログラムの発現を促通し、より質の高い運動を引き出す一助となる可能性がある。
6. 結論:運動連鎖の視点が理学療法の質を向上させる
本稿では、上肢の随意運動、特にリーチ動作を支える予測的姿勢調節(APA)について、「指先から体幹・下肢へと伝播する運動連鎖の制御」という視点から多角的に考察してきました。
複数の科学的エビデンスは、指先の微細な動きでさえも上肢全体を安定させる「分節的APA」を惹起し、さらに立位では体幹・下肢の「全身的APA」へと展開する、階層的かつ統合された制御システムの存在を一貫して示しています。この精緻な制御は、補足運動野(SMA)を中心とした大脳皮質、大脳基底核、小脳が連携する高度な神経ネットワークによって統括されています。
脳卒中リハビリテーションの臨床において、このAPAの視点は、運動障害の評価と治療に新たな次元をもたらします。対象者のリーチ動作を分析する際、単に主動作筋の出力や関節可動域だけでなく、その背景にある分節的・全身的APAの「破綻」を評価に含めることが、より本質的な問題点の抽出に繋がるでしょう。そして、本稿で提示した支持条件の操作や運動パラメータの多様化といった介入戦略は、APAという運動連鎖プログラムの「再建」を目的とした、より理論的根拠の強いアプローチを提供するものです。
予測的姿勢調節の深い理解と、それを臨床推論に組み込むことは、理学療法士が対象者の運動機能を最大限に引き出す上で不可欠な要素と言えます。
そもそも「予測的姿勢調節(APA)」とは、一言でいうと何ですか?
身体が「これから行う運動」によって生じるであろう姿勢の乱れを予測し、その乱れを打ち消すために、運動が始まる前に姿勢を制御する筋を活動させる、脳の先行準備プログラムのことです。フィードバック(事後修正)ではなく、フィードフォワード(事前準備)による制御である点が特徴です。
なぜ脳卒中リハビリテーションでAPAの理解が重要になるのですか?
脳卒中後のリーチ動作の拙劣さは、単なる筋力低下だけでなく、このAPAプログラムの破綻が大きく影響している可能性があるからです。運動の土台となる姿勢の準備がうまくできないために、代償動作が出現したり、動作が不安定になったりします。APAに着目することで、より本質的な運動障害の原因にアプローチできます。
「分節的APA」と「全身的APA」の違いは何ですか?
分節的APAは、運動を行う上肢そのものの中で生じる局所的な安定化機構です。例えば、手関節を動かす際に、先行して肘や肩の筋が活動し、腕全体の姿勢を保ちます。一方、全身的APAは、立位などで腕を動かす際に、体幹や下肢の筋が活動して身体全体のバランスを保つ、より大局的な安定化機構を指します。
APAの指令は、主に脳のどの部分が担っているのですか?
単一の部位ではなく、複数の領域が連携する脳内ネットワークによって制御されます。特に、運動のプランニングや順序付けを担う補足運動野(SMA)が中心的な役割を果たし、大脳基底核や小脳が運動の大きさやタイミングを調整、一次運動野が最終的な指令を出力すると考えられています。
臨床でAPAの障害を簡易的に評価する方法はありますか?
精密な機器がなくても、APAの障害を示唆する現象を観察することは可能です。例えば、立位で「素早く腕を前に挙げて」と指示した際に、腕の動きよりも先に体幹が大きく揺れたり、一歩足が出たりする場合は、全身的APAのタイミングや出力に問題がある可能性が考えられます。また、肘を固定したまま手首だけを素早く動かすよう指示した際に、肘や肩が大きく動揺してしまう場合は、分節的APAの機能不全が疑われます。
APAは、必ず主動作筋より先に活動するのですか?
自己のペースで運動を開始する際には、APAに関連する筋活動が主動作筋に先行することが多いです。しかし、合図に素早く反応するような課題(反応時間課題)では、両者の活動開始がほぼ同時になることもあります。重要なのは、時間的な先行関係そのものよりも、運動による外乱が本格的に影響を及ぼす前に、姿勢制御の指令がプログラムされているという点です。
ゆっくりとしたリーチ動作でもAPAは起こるのですか?
一般的にAPAは素早い運動において顕著に現れます。ゆっくりとした動きの場合、運動中に生じる姿勢の乱れは小さく、脳は先行的な準備をせずとも、感覚フィードバックに基づいた修正的な制御で十分に対応できるためです。
腕をどの方向に動かしても、APAのパターンは同じですか?
APAは「方向特異性」という顕著な特徴を持ちます。例えば立位で腕を前方に振る際には体幹・下肢の伸筋群が、後方に振る際には屈筋群が主に活動するなど、来るべき外乱の方向を相殺するために、動員される筋の組み合わせが全く異なります。
APAの再学習を促すリハビリの具体的な工夫はありますか?
感覚入力を調整する方法が有効です。例えば、立位でのリーチ練習の際に、非麻痺側の手で壁やテーブルに軽く触れさせる(ライトタッチ)と、それだけでAPAのパターンが変化し、姿勢が安定しやすくなることが報告されています。これは、触覚からの情報が姿勢を制御するための参照点として利用されるためで、APAの要求度を調整しながら運動学習を促すための一助となります。
指をタップするような、ごく小さな動きでもAPAは重要なのでしょうか?
はい、非常に重要です。たとえ穏やかな指のタップ動作であっても、それに先立って手首、肘、肩に至る上肢全体の筋群が協調して活動し、腕全体を安定させることが分かっています。これは、中枢神経系が精密な末端の動きを実現するためには、その土台となる近位部の安定がいかに重要であるかを理解し、事前に準備していることを示しています。
参考文献
- Aruin AS, Latash ML. Directional specificity of postural muscles in feed-forward postural reactions during fast voluntary arm movements. Exp Brain Res. 1995;103: 323–332.
doi:10.1007/bf00231718 - Bolzoni F, Bruttini C, Esposti R, Cavallari P. Hand immobilization affects arm and shoulder postural control. Exp Brain Res. 2012;220: 63–70.
doi:10.1007/s00221-012-3115-7 - Caronni A, Cavallari P. Anticipatory postural adjustments stabilise the whole upper-limb prior to a gentle index finger tap. Exp Brain Res. 2009;194: 59–66.
doi:10.1007/s00221-008-1668-2 - Chabran E, Fourment A, Maton B, Ribreau C. Chronology of upper limb anticipatory postural adjustments associated with voluntary wrist flexions and extensions in humans. Neurosci Lett. 1999;268: 13–16.
doi:10.1016/s0304-3940(99)00354-7 - Chabran E, Maton B, Ribreau C, Fourment A. Electromyographic and biomechanical characteristics of segmental postural adjustments associated with voluntary wrist movements. Influence of an elbow support. Exp Brain Res. 2001;141: 133–145.
doi:10.1007/s002210100823 - Cordo PJ, Nashner LM. Properties of postural adjustments associated with rapid arm movements. J Neurophysiol. 1982;47: 287–302.
doi:10.1152/jn.1982.47.2.287 - Cuisinier R, Olivier I, Nougier V. Effects of foreperiod duration on anticipatory postural adjustments: determination of an optimal preparation in standing and sitting for a raising arm movement. Brain Res Bull. 2005;66: 163–170.
doi:10.1016/j.brainresbull.2005.04.010 - Massion J. Movement, posture and equilibrium: interaction and coordination. Prog Neurobiol. 1992;38: 35–56.
doi:10.1016/0301-0082(92)90034-c - Slijper H, Latash M. The effects of instability and additional hand support on anticipatory postural adjustments in leg, trunk, and arm muscles during standing. Exp Brain Res. 2000;135: 81–93.
doi:10.1007/s002210000492 - Smith JA, Tain R, Sharp KG, Glynn LM, Van Dillen LR, Henslee K, et al. Identifying the neural correlates of anticipatory postural control: a novel fMRI paradigm. medRxiv. 2022. p. 2022.09.25.22280328.
doi:10.1101/2022.09.25.22280328
執筆者情報
三原拓(みはら たく)
ニューロスタジオ千葉 理学療法士
主な研究業績
2016,18年 活動分析研究大会 口述発表 応用歩行セクション座長
2019年 論文発表 ボバースジャーナル42巻第2号 『床からの立ち上がり動作の効率性向上に向けた臨床推論』
2022年. 書籍分担執筆 症例動画から学ぶ臨床歩行分析~観察に基づく正常と異常の評価法
p.148〜p.155 株式会社ヒューマン・プレス
その他経歴
2016年 ボバース上級講習会 修了
2024年 自費リハビリ施設 脳卒中リハビリパートナーズhaRe;Az施設長に就任
2025年 株式会社i.L入職 NEUROスタジオ千葉の立ち上げ
現在の活動
ニューロスタジオ千葉 施設長
脳卒中患者様への専門的リハビリ提供
療法士向け教育・指導活動
千葉ハンドリングセミナー共同代表

