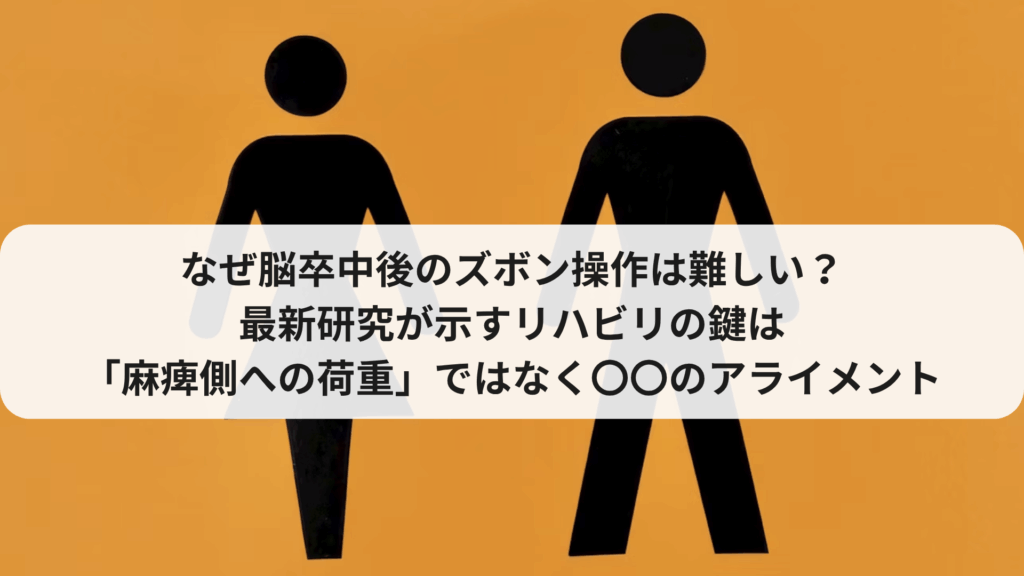
Contents
はじめに:臨床で繰り返される「ズボンが上がらない」3つのパターン
脳卒中後のリハビリテーションにおいて、患者の在宅復帰とQOL向上を左右する重要なADLの一つがトイレ動作です。その一連の動作の中でも、多くの患者が最後まで困難を抱え、療法士の介入が求められるのが、立位での「ズボンの引き上げ(下衣操作)」です。
近年の研究でも、トイレを構成する一連のタスクの中で「ズボンを履く (wearing pants)」動作が最も難易度が高いことが客観的に示されています。また、亜急性期の脳卒中患者を対象とした調査においても、「ズボンを引き下げる」「ズボンを上げて調整する」といった下衣操作は、入院時点で自立している患者が2割にも満たない、極めて難易度の高いサブタスクであることが報告されています。
臨床現場では、非麻痺側上肢を使い、なんとかズボンを上げようと試みるものの、うまくいかずにバランスを崩してしまう場面に頻繁に遭遇します。その失敗パターンには、いくつかの共通点が見られます。本稿では、臨床で散見される代表的な3つのパターンを提示し、その根本原因を探ることから始めたいと思います。
- パターン1:恐怖心とリーチ困難 麻痺側へ体重をかけることへの恐怖心が強く、体幹を非麻痺側に固めたまま、腕だけを伸ばそうと試みます。しかし、重心が麻痺側から離れすぎているため、そもそもズボンに手が届きません。加えて、ズボンが足に触れる感覚や、どこまで上がっているかという**知覚(皮膚感覚)**が鈍くなっているケースも見られます。
- パターン2:骨盤の不安定性 なんとか手を伸ばそうとしても、そのリーチ動作を支えるべき骨盤が不安定で、体幹の動きに追従してしまい、体全体が崩れてしまいます。リーチという分離された運動を行うための「土台」そのものがぐらついている状態です。脳卒中患者では、そもそも立位姿勢における骨盤の非対称性がバランス能力の低下と関連しているとの報告もあり、この土台の問題は根深いと考えられます。
- パターン3:荷重はできても「押し返せない」 麻痺側にゆっくりと体重を乗せることはできても、そこから床を力強く押し返して重心を非麻痺側へ戻すことができず、引き上げたズボンを保持したまま麻痺側へ崩れ落ちそうになります。これは、単に体重を「乗せる」ことと、そこから次の動きへと繋げる「推進する」ことが全く異なる能力であることを示唆しています。
これらの失敗パターンを解き明かす鍵は、単に「麻痺側へ体重を乗せる」という量的な問題だけではありません。本記事では、これらの臨床現象の根本原因を、近年報告されている複数の論文と照らし合わせながら多角的に分析し、全ての動作の基盤となる**「土台」のアライメントと、そこから生まれる質の高い運動制御*の重要性を解説します。そして、明日からの臨床に活かせる、より効果的なリハビリ戦略を提案します。
第1章:なぜ「麻痺側への荷重量」だけでは不十分なのか?
脳卒中後のリハビリテーションにおいて、麻痺側下肢への荷重を促し、左右対称的な立位姿勢を獲得することは、基本的なアプローチの一つです。多くの動作の基盤となる安定した立位を再建する上で、このアプローチの重要性は論を俟ちません。しかし、ズボンの引き上げという特異的なタスクにおいては、単純に「麻痺側への荷重量を増やす」ことだけを目標にすると、かえって動作改善の妨げになる可能性が近年の研究から示唆されています。
在宅で生活する脳卒中片麻痺者を対象としたある研究では、麻痺側下肢で体重を支える能力(最大荷重率)と、ズボン操作の巧緻性(動作遂行時間や持ち替え回数)との間には、有意な相関が認められなかったと報告されています。この研究は、「麻痺側への荷重能力の向上が、必ずしも下衣操作能力の向上にはつながらない」という重要な視点を提示しています。さらに、同研究では、下肢の麻痺が重度であるほど、静止立位時およびズボン操作時の両方で、非麻痺側への荷重優位の傾向が強かったことも明らかにされています。
この「非麻痺側荷重優位」の戦略は、必ずしも非効率な代償とは限りません。ある症例報告では、リハビリテーションを経てズボン操作の効率性(所要時間の短縮、持ち替え回数の減少)が改善したにもかかわらず、非麻痺側への荷重優位という非対称なパターンは残存したことが示されています。これは、患者が非麻痺側を主たる支持脚としながら、効率的な動作パターンを再学習した結果と解釈できます。
では、自立群と介助・監視群を分けるものは何なのでしょうか。その答えの一つが、荷重の「量」ではなく「質」、すなわち安定性にあります。ズボン操作が自立している群と監視を要する群の立位姿勢安定性を比較した研究では、両群の荷重率に有意差はなかったものの、監視群では左右方向への足圧中心(COP)の動揺範囲が有意に大きかったことが報告されています。これは、たとえ麻痺側にある程度の荷重ができていたとしても、その状態を安定して制御できなければ、転倒のリスクから監視が必要と判断されることを意味します。介助を要する群では、特に困難な麻痺側ズボンの操作時に麻痺側下肢の荷重率が低くなることも示されており、ダイナミックなタスクの中で安定して荷重し続けることの難しさがうかがえます。
これらの知見は、我々療法士に重要な問いを投げかけます。すなわち、ズボン操作の改善を目指す際、目標とすべきは荷重の「対称性」そのものなのか、それとも非対称な中でも安定して動作を完遂できる「制御能力」なのか、という問いです。本章での結論は、後者に重きを置くべきである、ということです。そのためには、単に荷重量を増やす量的アプローチから、動作の基盤となる感覚入力やアライメント制御といった質的アプローチへと視点を転換する必要があります。
第2章:動作の真の土台① – 感覚入力を司る「足部」の再評価
前章では、ズボン操作の成否が単なる麻痺側への荷重量だけでは決まらないことを確認しました。では、量的な荷重に代わる「質」的な要素とは何でしょうか。その答えの第一歩は、動作の土台となる「感覚入力」、特に足部からの情報処理にあります。
脳卒中患者は、姿勢制御を視覚情報に過度に依存する傾向が指摘されています。しかし、ズボンを引き上げるという行為は、視覚システムにとって一種の二重課題(デュアルタスク)です。視線はズボンや手元に向けられるため、姿勢を安定させるための視覚的フィードバックが著しく制限されます。この状況で安定性を保つには、視覚以外の感覚、すなわち足底からの体性感覚や前庭覚を効果的に利用する能力が不可欠となります。
この点において、非常に示唆に富む研究があります。脳卒中患者を対象としたある無作為化比較試験では、視覚情報を遮断したバランストレーニングを行った群は、視覚情報を利用した群に比べてバランス能力が有意に改善したと報告されています。これは、視覚入力を制限することによって、中枢神経系が体性感覚や前庭覚の情報を再重み付けし、より頑健な姿勢制御戦略を再学習することを示唆しています。
この「視覚に頼らないバランス能力」の重要性は、トイレ動作の自立度を直接的に調べた研究でも裏付けられています。トイレ動作の自立群と非自立群を比較した研究では、BBSの評価項目のうち「閉眼立位」の能力が、自立群において有意に高かったことが示されました。ズボン操作のように視線が手元に集中する課題では、まさにこの閉眼立位に近い状況下でのバランス能力が求められるのです。
では、その体性感覚の主要な入力源はどこか。言うまでもなく、立位姿勢における床との唯一の接点である「足部」です。我々は足部を単なる受動的な支持面として捉えがちですが、本来はアーチ構造を動的に制御し、地面の情報を鋭敏に感知する能動的な感覚器でもあります。
近年、この足部の能動的な役割を説明する概念として「フットコアシステム」が提唱されています。これは、体幹のコアマッスルが腰椎の安定性に関与するように、足部内在筋群が足部のアーチを局所的に安定させ、足ドームの形状変化に関する固有受容性情報を中枢へ送る上で重要な役割を担うという考え方です。このフットコアが機能することで、足部は変化する荷重に対して動的に応答し、安定した土台を提供することができます。
この理論は、具体的な介入研究によっても支持されています。扁平足を持つ対象者に対して、足部内在筋を鍛える「ショートフットエクササイズ(SFE)」を実施した群と、アーチサポートインソールを使用した群を比較した研究では、SFE群の方が足部アーチの改善と動的バランス能力の向上において、より効果的であったことが報告されました。これは、インソールのような受動的な支持だけでなく、内在筋への能動的なアプローチが、足部機能そのものを再教育する上で有効であることを示しています。
これらの知見をまとめると、ズボン操作の安定性を高めるためには、麻痺側への荷重をただ促すだけでなく、視覚への依存を減らし、足部からの感覚入力を最大限に活用できる状態を作ることが重要です。フットコアの概念に基づき、足部内在筋の機能を高めるアプローチは、そのための有効な一手となり得るでしょう。
第3章:動作の真の土台② – 体幹の動きを生み出す「骨盤・股関節」のアライメント
前章では、安定した動作の基盤として、足部からの質の高い感覚入力の重要性を論じました。しかし、その貴重な感覚情報は、頑健な「土台」に伝達されなければ、効果的な姿勢制御には繋がりません。立位姿勢において、下肢と体幹を連結するその土台こそが、「骨盤・股関節複合体」です。
導入部で提示した失敗パターン2のように、ズボンに手を伸ばそうとすると、体幹だけでなく骨盤まで一緒に回旋してしまい、身体全体が不安定になるケースは臨床で頻繁にみられます。これは、リーチに必要な「体幹の選択的な回旋」が失われ、体幹と骨盤が一つの塊(ブロック)として動いてしまう「分離不全」の状態です。
この現象は、近年のモーションキャプチャを用いた研究によって、その運動学的特徴が明らかになってきています。ズボン操作の自立群と介助群を比較した研究では、介助群は麻痺側への操作時に、骨盤に対する体幹の相対的な回旋角度が有意に小さく、一方で空間に対する骨盤そのものの回旋角度が有意に大きかったことが報告されました。つまり、介助群は、安定した骨盤の上で体幹を捻るのではなく、股関節を支点として骨盤ごと身体を回旋させることで、非効率なリーチを行っていたのです。
では、なぜこのような分離不全が生じるのでしょうか。その根底には、リーチ動作の土台となるべき骨盤・股関節の不安定性があります。選択的な体幹回旋は、腹斜筋群などの回旋筋群が活動する際、骨盤が股関節周囲筋(特に中殿筋など)によって下肢に対してしっかりと固定されていることが前提となります。この固定が不十分だと、体幹を回旋させる力が骨盤を安定させる力を上回ってしまい、結果として骨盤ごと回ってしまうのです。
さらに、骨盤のアライメントそのものが、体幹の運動性を規定することも重要です。健常者を対象とした研究では、骨盤を中間位から前傾または後傾させると、いずれの肢位でも脊柱の回旋可動域が有意に減少したことが示されています。脳卒中患者に散見される骨盤の過度な前後傾は、ズボン操作に必要な体幹の回旋能力を、構造的に制限してしまっている可能性があるのです。また、骨盤の左右非対称な変位が大きいほど、バランス能力や歩行能力が低下するという報告もあり、アライメントの異常が機能低下に直結することがわかります。
これらの骨盤・股関節機能の問題は、ズボンに手を伸ばす「下方リーチ」の効率性にも影響を及ぼします。効率的な下方リーチは、腰椎と股関節の協調した屈曲によって行われます。しかし、股関節の安定性や可動性が低い患者では、股関節の屈曲を最小限にし、腰椎の過剰な屈曲だけでリーチしようとする非効率なパターンに陥りがちです。これは重心を不必要に前方へ移動させ、バランスを不安定にするだけでなく、腰部への力学的ストレスも増大させます。
したがって、ズボン操作におけるリーチや体幹回旋を練習する以前の段階として、まずは「安定した骨盤・股関節」という土台を評価し、構築することが不可欠です。立位での骨盤アライメントを評価し、股関節周囲の安定性を高める介入を行うことが、その後の選択的な体幹運動を引き出し、効率的で安全なズボン操作を可能にするための重要な鍵となります。
第4章:非麻痺側へのアプローチという視点 – AP方向の制御が鍵
これまでの章で、動作の土台となる足部や骨盤・股関節の重要性について論じてきました。これらの要素は、特に麻痺側の機能に着目したものでした。しかし、片手でズボンを上げるという非対称な動作を遂行する上で、我々は見過ごされがちなもう一つの重要な要素、すなわち「非麻痺側」の役割に目を向ける必要があります。
臨床上、非麻痺側は単に体重を預ける「支え」と見なされがちです。しかし、近年の研究は、非麻痺側がより能動的かつ巧みに姿勢を制御する「コントローラー」としての役割を担っていることを示唆しています。
ある脳卒中患者のズボン操作能力の改善過程を追った症例報告は、この点に関して興味深いデータを提供しています。リハビリテーションによって患者のズボン操作がより効率的になった際、運動学的に最も顕著な変化が見られたのは、麻痺側ではなく非麻痺側でした。具体的には、非麻痺側下肢の足圧中心(COP)が、特に前後方向(Anterior-Posterior; AP)において、より速く、より広範囲に移動できるようになったのです。ズボンを下げたり上げたりする際には、重心を前後へダイナミックに移動させる必要があります。この研究は、その重心移動を巧みに制御しているのが、まさに非麻痺側下肢であることを示唆しています。実際に、非麻痺側下肢で安定した立位を獲得できれば、麻痺の重症度に関わらず下衣操作は獲得できる可能性があると結論付けた研究もあり、非麻痺側の安定性・制御能力の重要性がうかがえます。
さらに注目すべきは、「非麻痺側への介入が、麻痺側を含む全身の制御に好影響を及ぼす」という可能性です。これは、大脳半球間の相互作用や両側性の運動制御の観点から説明できます。
脳卒中患者を対象に、非麻痺側の上肢を用いた運動課題(メディシンボールを前方に押す)を実施した研究では、わずか1回の練習セッションの後に、予測的姿勢調節(Anticipatory Postural Adjustments; APA)が改善したことが報告されています。重要なのは、その改善が非麻痺側だけでなく、麻痺側の体幹や下肢筋においても、活動開始タイミングが有意に早まるという両側性の効果として現れたことです。APAは、リーチなどの素早い運動に先立って姿勢を安定させるための重要な神経メカニズムであり、この機能が非麻痺側への介入によって両側性に改善することは、臨床的に大きな意味を持ちます。
これらの知見から、ズボン操作のリハビリテーション戦略として、麻痺側の機能回復を目指すアプローチに加え、「非麻痺側の制御能力を最大限に引き出す」アプローチを意図的に組み込むことが有効であると考えられます。これは単なる代償戦略の助長ではありません。非麻痺側下肢での前後方向へのステップ練習やリーチ練習といった課題は、タスク遂行の直接的な練習になるだけでなく、両側性の姿勢制御ネットワークを賦活化させるトリガーとなり得るのです。臨床では、麻痺側と非麻痺側、どちらか一方を問題と決めつけるのではなく、両者の相互作用を評価し、介入の糸口を探る視点が重要となります。
第5章:運動連鎖の最終出力 – 選択的な体幹回旋を引き出す「脊柱アライメント」
これまで、感覚入力を担う「足部」、動作の土台となる「骨盤・股関節」、そして姿勢制御のコントローラーとしての「非麻痺側」の役割を解説してきました。最終章では、これらの要素がいかにして統合され、ズボン操作という最終的な動作、すなわち「選択的な体幹回旋」として出力されるのか、運動連鎖の視点から考察します。
ズボンを片手で引き上げるためには、非麻痺側の手を麻痺側の下肢へとリーチさせる必要があります。この時、身体の他の部分ができるだけ安定性を保ったまま、体幹だけが滑らかに回旋することが理想的な運動です。しかし、第3章で述べたように、介助を要する患者では体幹と骨盤が分離せず、一つの塊として回旋してしまう現象がみられます。この非効率な運動パターンを改善する鍵は、脊柱そのもののアライメントにあります。
健常者を対象とした基礎研究が、この関係を明確に示しています。その研究によると、脊柱の回旋可動域は、骨盤が中間位にある時に最も大きく、前傾位や後傾位では有意に減少することが報告されています。これは、脊柱が力学的に最も効率よく可動できるのは、生理的な弯曲が保たれた中間位(ニュートラル)であることを意味します。ズボン操作に必要な体幹回旋を最大限に引き出すためには、その前提条件として、脊柱が中間位に保たれていることが不可欠なのです。
そして、この理想的な脊柱アライメントは、これまでの章で解説してきた「土台」からのボトムアップの運動連鎖によって作り上げられます。すなわち、①機能的な足部が床からの情報を正確に捉え、②安定した股関節が骨盤の過度な傾斜や動揺を制御し、③両側の下肢が適切に床反力を生み出すことで、骨盤は中間位に安定します。この安定した骨盤の上に、初めて脊柱は中間位として乗り、自由な回旋運動を獲得できるのです。腰痛患者を対象とした研究でも、腰椎と股関節の協調運動(運動連鎖)の破綻が指摘されており、この部位の連携がいかに重要であるかがわかります。
臨床では、この運動連鎖の破綻を評価することが重要です。患者がズボンを上げようとする際、骨盤が過度に前傾し腰椎が前彎していないか、あるいは骨盤が後傾し円背傾向になっていないか。麻痺側下肢がバックニー(膝の過伸展)を呈していないか。これらの代償的なアライメントは、股関節や体幹の支持性が不十分なために、関節のロック機構に頼って安定性を得ようとする戦略の結果です。しかし、それは同時に脊柱を非効率なアライメントに固定し、ズボン操作に最も必要な体幹の回旋運動を阻害してしまうのです。
したがって、我々のアプローチは、単に「体幹を捻る」練習を繰り返すことではありません。足部から骨盤、そして下肢全体へとアプローチし、安定した土台を再構築することで、結果として脊柱が中間位に導かれ、選択的な体幹回旋が「自然に現れる」状態を目指すことが、より本質的な戦略と言えるでしょう。
FAQ(よくある質問)
Q1. 結局、麻痺側に体重をかける練習は必要ないのですか?
A. いいえ、麻痺側への荷重練習は非常に重要です。本記事でお伝えしたかったのは、その練習の「目的」をより深く理解することの重要性です。
単に体重を乗せるだけでなく、その荷重が「安定した骨盤」を作り出し、上半身のリーチ動作を支える土台となることが真の目的です 。自立している方は、介助が必要な方よりも有意に麻痺側への荷重率が高いというデータもあります 。
ただし、がむしゃらに荷重を増やすだけでは、はじめに紹介した「押し返せない」といった問題は解決しません。荷重の「量」と共に、その「質」を高める視点、すなわちフットコアの機能を高めるアプローチを組み合わせることが、より効果的なリハビリにつながります。
Q2. 「フットコア」を鍛える簡単な方法はありますか?
A. はい、最も基本的で重要なエクササイズとして**「ショートフットエクササイズ(SFE)」**が挙げられます 。これは、足裏のアーチを意識的に引き上げることで、足部内在筋を直接的に活性化させるトレーニングです。
【簡単なやり方】
- 椅子に座り、足を床につけます。
- 足の指を曲げずに、母趾球(親指の付け根)を踵(かかと)の方向に引き寄せるように力を入れ、土踏まずにアーチを作ります(ドーム状に持ち上げます)。
- その状態を数秒間キープします。
この運動は、足部内在筋の活動を高め、動的なバランス能力を向上させることが報告されています 。慣れてきたら、立った状態や片足立ちでも行い、より実践的な状況でフットコアを機能させる練習へと発展させていきます。
Q3. なぜ非麻痺側(良い方)の練習も重要なのでしょうか?
A. 非麻痺側へのアプローチは、単なる代償動作の練習以上の、2つの重要な意味を持ちます。
- 高度なスキルを持った主役としての役割: ズボン操作が改善した症例では、非麻痺側が体の前後方向の揺れを巧みにコントロールするスキルを学習していたことが報告されています 。非麻痺側をより巧みに使えるようになること自体が、動作自立への近道となります。
- 脳の姿勢制御システム全体を再学習させる「治療の入り口」としての役割: 最も注目すべきは、非麻痺側の腕を使った練習によって、練習していない麻痺側を含めた全身の「予測的姿勢調節(APA)」のタイミングが改善したという研究結果です 。これは、非麻痺側への適切な介入が、脳の根幹的なプログラムに働きかけ、全身のパフォーマンス向上に寄与する**「転移」**が起こる可能性を示しています。
したがって、麻痺側の機能回復を目指すアプローチと、非麻痺側のスキルアップおよび脳機能全体への働きかけを目的としたアプローチを両立させることが、より確実な自立につながると言えます。
まとめ:明日からの臨床を変える3つの視点
本稿では、脳卒中後のズボン操作困難の背景にある要因を、複数の研究知見を基に多角的に考察してきました。単に「麻痺側へ荷重する」という量的なアプローチには限界があり、より質の高い運動制御に着目する必要があることを論じてきました。明日からの臨床実践に向けて、本稿で提案する3つの視点を以下にまとめます。
-
- 視点を「土台」へ下ろす:足部と骨盤を再評価する
動作の不安定さが体幹や上肢に見られたとしても、その原因はより下方にあることが少なくありません。まずは、床からの感覚入力を担う「足部(フットコア)」の機能と、体幹の動きの基盤となる「骨盤・股関節」の安定性・アライメントを評価し、介入の出発点とすることが重要です。
- 「非麻痺側」をコントローラーとして活用する
非麻痺側は単なる支持基盤ではなく、姿勢を能動的に制御する役割を担っています。特に前後方向への重心移動能力は、ズボン操作の効率性と密接に関連します。非麻痺側への積極的なアプローチが、両側性の姿勢制御ネットワークを賦活化させ、結果として麻痺側のパフォーマンス向上にも寄与する可能性を考慮に入れます。
- 運動の「結果」ではなく「前提条件」を整える
「体幹を回旋させる」という最終的な動作そのものを練習する前に、その運動が可能になるための「前提条件」が満たされているかを確認します。すなわち、適切な感覚入力と安定した土台によって、脊柱がニュートラルなアライメントに導かれているか、という点です。運動連鎖の観点から全身を捉え、ボトムアップでアプローチすることが、質の高い動作の再学習に繋がります。
- 視点を「土台」へ下ろす:足部と骨盤を再評価する
ズボン操作の自立は、患者の尊厳と自信を回復させる上で極めて大きな一歩です。本稿で紹介した多角的な視点が、日々の臨床における評価・介入のヒントとなり、一人でも多くの患者様の生活再建に繋がることを願っています。
参考文献
- Kawanabe E, Suzuki M, Tanaka S, Sasaki S, Hamaguchi T. Impairment in toileting behavior after a stroke. Geriatr Gerontol Int. 2018;18: 1166–1172. https://doi.org/10.1111/ggi.13435
- Kitamura S, Otaka Y, Murayama Y, Ushizawa K, Narita Y, Nakatsukasa N, et al. Differences in the difficulty of subtasks comprising the toileting task among patients with subacute stroke: A cohort study. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2023;32: 107030. https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2023.107030
- Koike Y, Sumigawa K, Koeda S, Shiina M, Fukushi H, Tsuji T, et al. Approaches for improving the toileting problems of hemiplegic stroke patients with poor standing balance. J Phys Ther Sci. 2015;27: 877–881. https://doi.org/10.1589/jpts.27.877
- Kong SW, Jeong YW, Kim JY. Correlation between balance and gait according to pelvic displacement in stroke patients. J Phys Ther Sci. 2015;27: 2171–2174. https://doi.org/10.1589/jpts.27.2171
- 岩田研二, 岡西哲夫, 山崎年弘, 倉田昌幸, 河村樹里, 他. 在宅脳卒中片麻痺者の排泄動作自立者における下衣操作能力の検討. PTジャーナル. 2012;46(12): 1137–1142.
- Hiragami S, Nagahata T, Koike Y, Inoue Y. Lower garment-lifting postural control characteristics during toilet-related activities in healthy individuals and a post-stroke hemiplegic patient undergoing rehabilitation. J Phys Ther Sci. 2018;30: 1462–1467. https://doi.org/10.1589/jpts.30.1462
- 鳥居誠志, 石岡俊之, 小池祐士, 濱口豊太, 中村裕美. 足圧中心解析による脳卒中片麻痺者が片手でズボンを上げる工程の立位姿勢安定性. 作業療法. 2019;38(6): 654–662. https://doi.org/10.32178/jotr.38.6_654
- Kuroda Y, Motojima N, Yamamoto S. Analysis of movements involved in raising lower garments during toileting in patients with stroke and hemiplegia: An analysis focused on manipulation on the paretic side. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2024;120: 106364. https://doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2024.106364
- Bonan IV, Yelnik AP, Colle FM, Michaud C, Normand E, Panigot B, et al. Reliance on visual information after stroke. Part II: Effectiveness of a balance rehabilitation program with visual cue deprivation after stroke: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil. 2004;85: 274–278. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2003.06.016
- 米持利枝, 前野恭子, 江西一成. 脳卒中片麻痺患者におけるトイレ動作の自立に対する立位バランスの影響. 愛知県理学療法学会誌. 2017;29(2): 76-80.
- McKeon PO, Hertel J, Bramble D, Davis I. The foot core system: a new paradigm for understanding intrinsic foot muscle function. Br J Sports Med. 2015;49: 290. https://doi.org/10.1136/bjsports-2013-092690
- Kim E-K, Kim JS. The effects of short foot exercises and arch support insoles on improvement in the medial longitudinal arch and dynamic balance of flexible flatfoot patients. J Phys Ther Sci. 2016;28: 3136–3139. https://doi.org/10.1589/jpts.28.3136
- Kusoffsky A, Apel I, Hirschfeld H. Reaching-lifting-placing task during standing after stroke: Coordination among ground forces, ankle muscle activity, and hand movement. Arch Phys Med Rehabil. 2001;82: 650–660. https://doi.org/10.1053/apmr.2001.22611
- 和田治, 建内宏重, 市橋則明. 骨盤の矢状面アライメントが骨盤・体幹の回旋可動性および身体重心移動量に与える影響. 理学療法学. 2009;36(7): 356–362. https://doi.org/10.15063/rigaku.kj00005931384
- Fujita T, Sato A, Iokawa K, Yamane K, Yamamoto Y, Ohira Y, et al. Quantifying lower extremity and trunk function for dressing in stroke patients: a retrospective observational study. Top Stroke Rehabil. 2018;25: 1–4. https://doi.org/10.1080/10749357.2018.1426240
- 岩田研二, 木村圭佑, 愛甲幸代, 木庭翠, 河村樹里, 倉田昌幸, et al. 脳卒中片麻痺患者における排泄動作の検討. 理学療法学Supplement. 2010;2009: B3O1086. https://doi.org/10.14900/cjpt.2009.0.b3o1086.0
- Curuk E, Lee Y, Aruin AS. Individuals with stroke improve anticipatory postural adjustments after a single session of targeted exercises. Hum Mov Sci. 2020;69: 102559. https://doi.org/10.1016/j.humov.2019.102559
- Shum GLK, Crosbie J, Lee RYW. Movement coordination of the lumbar spine and hip during a picking up activity in low back pain subjects. Eur Spine J. 2007;16: 749–758. https://doi.org/10.1007/s00586-006-0122-z
執筆者情報
三原拓(みはら たく)
ニューロスタジオ千葉 理学療法士
主な研究業績
2016,18年 活動分析研究大会 口述発表 応用歩行セクション座長
2019年 論文発表 ボバースジャーナル42巻第2号 『床からの立ち上がり動作の効率性向上に向けた臨床推論』
2022年. 書籍分担執筆 症例動画から学ぶ臨床歩行分析~観察に基づく正常と異常の評価法
p.148〜p.155 株式会社ヒューマン・プレス
その他経歴
2016年 ボバース上級講習会 修了
2024年 自費リハビリ施設 脳卒中リハビリパートナーズhaRe;Az施設長に就任
2025年 株式会社i.L入職 NEUROスタジオ千葉の立ち上げ
現在の活動
ニューロスタジオ千葉 施設長
脳卒中患者様への専門的リハビリ提供
療法士向け教育・指導活動
千葉ハンドリングセミナー共同代表

