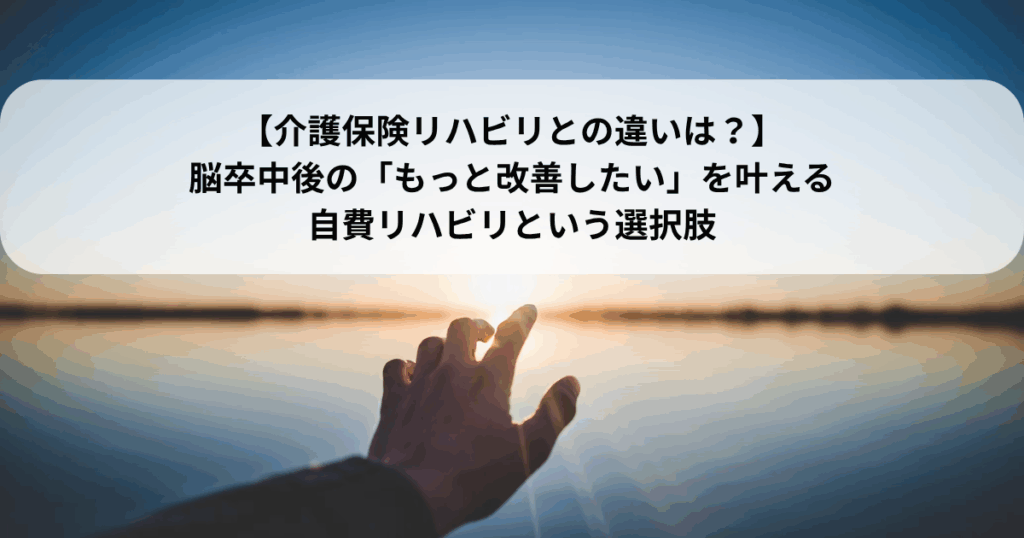
回復期リハビリ病院からの退院後、現在利用されている介護保険サービスの内容や時間に、物足りなさを感じる方も多いのではないでしょうか。
実際、私たちが運営するNEUROスタジオ(大阪・東京・千葉)でも、「もっと本格的なリハビリを受けたい」「このままで良くなるのか不安だ」といった切実な思いから、お問い合わせをいただくケースが後を絶ちません。
なぜ、多くの方が「物足りなさ」を感じるのか?
例えば、デイサービスの個別リハビリは1回15分程度のマッサージが中心であったり、訪問リハビリで専門家と関われる時間は、週に最大でも120分と定められています。場合によっては、担当するスタッフが必ずしも理学療法士や作業療法士の国家資格を持っていないケースもあります。
この問題の根源は、介護保険制度の「目的」そのものにあります。
介護保険制度では、積極的な「改善」を目指すことよりも、まずはご自宅での「生活の維持・安定」を支えることを第一の目的として設計されているためです。そのため、多くの事業所では脳卒中リハビリに対する深い専門性よりも、高齢者ケア全般の幅広い知識が求められる傾向にあります。
その結果、神経活動の活性化(神経可塑性)に不可欠とされるリハビリの『量(頻度・時間)』と『質(専門性・個別性)』が、改善を目指す上ではどうしても不足しがちになる、という状況が生まれやすいのです。
目的
△ 介護保険リハビリ
生活の維持・安定が目的
◎ NEUROスタジオ
積極的な心身機能・能力の改善
頻度・時間
△ 介護保険リハビリ
制度上の制約が大きい
(例:個別リハ1回15分程度)
◎ NEUROスタジオ
目標達成の期間に合わせて
自由に頻度と時間を設定
専門性
△ 介護保険リハビリ
脳卒中の専門性より
横断的な分野が優先される
◎ NEUROスタジオ
脳卒中に特化した療法士
(スペシャリスト)
担当者
△ 介護保険リハビリ
指名不可のことが多い
◎ NEUROスタジオ
専門性の強い療法士が担当
指名も可能
リハビリ内容
△ 介護保険リハビリ
集団リハやマッサージが中心に
◎ NEUROスタジオ
完全1対1での神経科学的アプローチ
この記事のポイント
本記事では、この『量』と『質』がなぜ改善に不可欠なのかを、最新の科学的根拠(エビデンス)に基づいて解説します。その上で、介護保険の枠を超え、あなたの「もっと改善したい」という目標を達成するための具体的な選択肢を明らかにします。
「もう何年も経っているから…」と、諦めかけてはいませんか? ご安心ください。脳卒中発症から23年が経過した方でも、機能が改善したという驚くべき事例も報告されています。
この記事では、そうした希望の根拠も詳しく解説していきます。 現状のリハビリに課題を感じている方へ、この記事が次の一歩を踏み出すための判断材料となることを目指します。
なぜ「6ヶ月」という常識が生まれたのか?
この「6ヶ月の壁」という言葉には、「制度的な背景」と「科学的な背景」の2つの側面があります。
まず「制度的な背景」として、日本の医療保険制度では、脳卒中後のリハビリテーションを行う「回復期リハビリテーション病棟」への入院期間が、おおむね150日〜180日と定められています。多くの方がこの期間で集中的なリハビリを終えるため、「約6ヶ月が一つのタイムリミット」という認識が広く浸透しました。
そして、この制度の根拠ともなったのが「科学的な背景」です。 特に、1990年代に行われた大規模な臨床研究(コペンハーゲン・脳卒中研究)では、多くの患者さんの運動機能が、発症後最初の3ヶ月で最も大きく改善し、その速度は6ヶ月を過ぎると非常に緩やかになることが報告されました(Jørgensen HS et al., Arch Phys Med Rehabil, 1995など)。
この図のように「回復のカーブが6ヶ月でなだらかになる」という研究結果が、『最初の6ヶ月が勝負』という考え方の科学的な裏付けとなり、現在の医療制度にも大きな影響を与えました。そして、これが転じて「6ヶ月以降は良くならない」という誤った常識が広まった一因になったのかもしれません。
「後遺症の改善が終わる」のではなく「リハビリ環境の変化」
では、6ヶ月を過ぎると、本当に改善は止まってしまうのでしょうか。
ここで絶対に混同してはならないのが、「改善のペースが緩やかになること」と「完全に停止すること」は全く違う、という事実です。
近年のリハビリテーション科学では、“6ヶ月の壁”の本当の正体は、神経が活性化される能力そのものが尽きたのではなく、退院によってリハビリの『量』と『質』が劇的に低下する、という環境の変化であるという見方が主流になっています。
「神経可塑性」は、適切なトレーニングによっていつでも引き出すことが可能です。しかし、そのためには「集中的で、反復的なリハビリ」が必要不可欠であることも、多くの研究で示されています(Takeuchi & Izumi, 2013など)。
つまり、例えるなら一度鍛えた筋肉も、トレーニングをやめれば衰えてしまうのと同じです。脳の神経が変化する力そのものが消えたのではなく、神経活動を鍛えるための適切なトレーニング(リハビリ)が足りなくなってしまった状態と言えるのです。
「6ヶ月の壁」を科学的に突破する、脳科学に基づいた2つの鍵

「6ヶ月の壁」の正体が、脳の能力の限界ではなく、リハビリ環境の変化にあることはご理解いただけたかと思います。
では、止まってしまったトレーニングを再開し、再び脳を鍛え始めるには、具体的にどうすればいいのでしょうか。その鍵は、脳科学に基づいた2つのアプローチにあります。
鍵①:脳を再び目覚めさせる、圧倒的なリハビリの「量」
脳が持つ、経験に応じて自らの構造や機能を変える性質を「神経可塑性」と呼びます。この神経可塑性を最大限に引き出すには、一定量以上のリハビリ、つまり脳への刺激量が不可欠です。
これは単なる精神論ではなく、数多くの研究で証明されています。
例えば、リハビリの「量」と「効果」の関係を調べた研究では、リハビリ時間を増やせば増やすほど上肢の機能が改善するという、明確な「用量反応関係(Dose-Response Relationship)」があることが示されています(Lang et al., 2016)。これは、薬の量が多いほど効果が高まるのと同じように、リハビリも量をこなすことが直接的に結果に結びつくことを意味します。
さらに、数ある研究の中でも最も信頼性が高いとされる「コクランレビュー」においても、「反復課題トレーニング」、つまり十分な量を反復してこなすことが、機能の改善に有効であると結論づけられているのです(French et al., 2016)。
つまり、「6ヶ月の壁」を越えるための最初の鍵は、介護保険の枠内では確保が難しい、絶対的なリハビリの量を確保することにあります。
鍵②:神経の”再配線”を精密に促す、専門的なリハビリの「質」
しかし、ただ闇雲に時間をかけて量をこなせば良い、というわけではありません。「6ヶ月の壁」を突破するためのもう一つの鍵、それはリハビリの「質」です。
一回一回の動きの質が、脳の神経回路が正しく再編成される(=再配線される)ために極めて重要になります。
脳卒中後、多くの方が麻痺した手足を動かそうとする際、無意識に他の部分の力を使って補おうとします。これを「代償動作」と呼びます。この代償動作は、短期的には動かせたように見えても、長期的には異常な運動パターンを脳に定着させてしまい、本来の滑らかな動きの回復を妨げる「不適応な可塑性(maladaptive plasticity)」を引き起こす可能性があります。頑張っているのに努力が報われない可能性があるのが脳卒中後遺症のリハビリの難しさでもあり、だからこそ専門家による質の高いアプローチが不可欠なのです。
最近の研究では、理学療法士による「個別指導」の運動療法を2ヶ月間行ったことで、慢性期の方の歩行が有意に改善したと報告されています(Yoshioka et al., 2022)。また、私たちが実践するリハビリは、常に最新の臨床実践ガイドライン(Hornby et al., 2020)といった科学的根拠に基づいています。
つまり、「6ヶ月の壁」を越えるための第二の鍵は、代償動作を最小限に抑え、正しい運動学習を促すための、専門性の高い療法士と共に実施する質の高いリハビリを確保することなのです。
NEUROスタジオの科学的リハビリ戦略
脳卒中後遺症の壁、特に「6ヶ月の壁」を突破するためには、「量」と「質」という2つの鍵が不可欠であることを解説してきました。
では、この鍵を現実の場でどのようにして手に入れればいいのでしょうか。それこそが、介護保険サービスと、NEUROスタジオが提供する価値の決定的な違いです。
戦略的な「量」の確保:介護保険に“上乗せ”するリハビリ時間
介護保険のリハビリは、ご自宅での生活を支える上で非常に重要です。その大切な基盤を維持しながら、科学的根拠が示す、改善に必要なリハビリの量を確保するために、足りない部分を自費リハビリで「上乗せ」する。これが効果的な選択肢だと考えています。
介護保険の訪問リハビリでは週に最大120分という上限がありますが、NEUROスタジオでは、あなたの目標達成に必要なリハビリ量を、その制約なく柔軟に設定できます。
さらに、リハビリを行う場所もスタジオに限りません。ご自宅はもちろん、職場復帰を目指した勤務先での実践的な練習や、外出同行など、あなたの目標に合わせた場所でリハビリを行うことも可能です(→料金プランはこちら)。
戦略的な「質」の追求:介護保険では得られない専門家による1対1のアプローチ
NEUROスタジオでは、臨床10年以上の認定理学療法士(脳卒中)が数多く在籍しており、脳卒中リハビリに対して実績と強い専門性を持つスタッフが、完全マンツーマンで利用者様とのリハビリを責任を持って担当します。
当施設では利用者様の姿勢や運動の癖や代償動作を的確に分析し、神経可塑性を最大限に引き出すためのアプローチを、現場で微調整しながら提供します。これは、集団でのリハビリや、短い時間での関わりでは難しい、1対1の環境だからこそ実現できる、質の高いリハビリです。
希望は現実になる。科学が示す「慢性期でも良くなる」という事実

ここまで、「6ヶ月の壁」の正体と、それを突破するための「量」と「質」という鍵について解説してきました。
しかし、理論だけでは「本当に自分も良くなるのだろうか」という不安は消えないかもしれません。 この章では、その希望が単なる気休めではなく、科学的に証明された現実であることを、具体的な研究報告と共にお伝えします。
発症から23年後の機能改善事例
導入部で少しだけ触れた、驚くべき報告をご紹介します。 2017年に発表された研究で、脳卒中を発症してから実に23年が経過した患者さんが、集中的なリハビリによって運動機能の改善を示した、という事例です(Sörös et al., 2017)。
この事実は、「もう何年も経ってしまったから手遅れだ」という考えが、必ずしも正しくないことを示す、何よりの証拠と言えるでしょう。
数多くの研究が証明する「改善の可能性」
この23年後の事例は、決して奇跡的な例外ではありません。 「発症から長期間が経過した慢性期であっても、リハビリは有効である」ということは、数多くの研究によって繰り返し示されています。
例えば、複数の研究結果を統合して分析する、最も信頼性の高い研究手法の一つである「メタ解析」においても、慢性期における理学療法が運動機能を有意に改善させることが結論づけられています(Ferrarello et al., 2011)。
また、近年の追跡調査でも、回復は発症後早期に最も大きいものの、慢性期においても改善は継続することが報告されており(Borschmann & Hayward, 2020)、もはや「6ヶ月以降は良くならない」という考えは過去の常識となりつつあります。
大切なのは、適切な「量」と「質」のリハビリを、諦めずに続けることです。お身体には、まだまだ可能性が眠っています。
結論:改善はまだ終わっていない
ここまで、「6ヶ月の壁」という“常識”の正体と、それを科学的に突破するための具体的な方法について解説してきました。
この記事でお伝えしたかった、最も重要なメッセージはこれです。
6ヶ月の壁”は、あなたの身体に訪れた伸び代の限界ではありません。
それは、退院などを機に、リハビリの「量」と「質」が低下してしまった「環境の壁」に他なりません。
そして、その壁は、科学的根拠に基づいた適切なリハビリ、つまり、あなたの脳に残された「神経可塑性」を再び目覚めさせるための十分な「量」と、正しい方向へと導く専門的な「質」によって、乗り越えることが可能です。
身体に残された可能性を、「もう半年経ったから」という言葉だけで諦めないでください。
まずは、あなたが今感じていること、そして「もっとこうなりたい」という目標をNEUROスタジオにお聞かせいただけませんか。初回体験で、その新たな一歩を踏み出しましょう。
諦めていたその症状、
まだ「変化」の余地があります。
リハビリの効果が停滞していると感じていませんか?
NEUROスタジオでは、脳科学に基づいたアプローチで
あなたの眠っている改善の可能性を引き出します。
参考文献
Jørgensen HS, Nakayama H, Raaschou HO, et al. Outcome and time course of recovery in stroke. Part II: Time course of recovery. The Copenhagen Stroke Study. Arch Phys Med Rehabil. 1995;76: 406–412.
(和訳)脳卒中におけるアウトカムと回復のタイムコース。Part II:回復のタイムコース。コペンハーゲン脳卒中研究
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7741609/
Takeuchi N, Izumi SI. Rehabilitation with poststroke motor recovery: a review with a focus on neural plasticity. Stroke Res Treat. 2013;2013: 128641.
(和訳)脳卒中後の運動回復におけるリハビリテーション:神経可塑性を中心としたレビュー
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3659508/
Lang CE, Strube MJ, Bland MD, et al. Dose response of task-specific upper limb training in people at least 6 months poststroke: A phase II, single-blind, randomized, controlled trial. Ann Neurol. 2016;80: 342–354.
(和訳)発症後6ヶ月以上の脳卒中患者における課題特異的上肢トレーニングの用量反応関係:第II相単盲検ランダム化比較試験
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5016233/
French B, Thomas LH, Coupe J, et al. Repetitive task training for improving functional ability after stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2016;11: CD006073.
(和訳)脳卒中後の機能的能力を改善するための反復課題トレーニングhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27841442/
Yoshioka K, Watanabe T, Maruyama N, et al. Two-month individually supervised exercise therapy improves walking speed, step length, and temporal gait symmetry in chronic stroke patients: A before-after trial. Healthcare (Basel). 2022;10: 527.
(和訳)2ヶ月間の個別指導運動療法は慢性期脳卒中患者の歩行速度、歩幅、時間的対称性を改善する:前後比較試験
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8948174/
Hornby TG, Reisman DS, Ward IG, et al. Clinical Practice Guideline to Improve Locomotor Function Following Chronic Stroke, Incomplete Spinal Cord Injury, and Brain Injury. J Neurol Phys Ther. 2020;44: 49–100.
(和訳)慢性期脳卒中、不全脊髄損傷、脳損傷後の歩行機能を改善するための臨床実践ガイドライン
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6944934/
Sörös P, Teasell R, Hanley DF, Spence JD. Motor recovery beginning 23 years after ischemic stroke. J Neurophysiol. 2017;118: 778–781.
(和訳)虚血性脳卒中から23年後に始まった運動回復
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28515288/
Ferrarello F, Baccini M, Rinaldi LA, et al. Efficacy of physiotherapy interventions late after stroke: a meta-analysis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2011;82: 136–143.
(和訳)脳卒中後期の理学療法介入の有効性:メタ解析
https://jnnp.bmj.com/content/82/2/136
Borschmann KN, Hayward KS. Recovery of upper limb function is greatest early after stroke but does continue to improve during the chronic phase: a two-year, observational study. Physiotherapy. 2020;107: 216–223.
(和訳)上肢機能の回復は脳卒中後早期に最も大きいが、慢性期においても改善は継続する:2年間の観察研究
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32026823/
執筆者情報
三原拓(みはら たく)
ニューロスタジオ千葉 理学療法士
主な研究業績
2016,18年 活動分析研究大会 口述発表 応用歩行セクション座長
2019年 論文発表 ボバースジャーナル42巻第2号 『床からの立ち上がり動作の効率性向上に向けた臨床推論』
2022年. 書籍分担執筆 症例動画から学ぶ臨床歩行分析~観察に基づく正常と異常の評価法
p.148〜p.155 株式会社ヒューマン・プレス
その他経歴
2016年 ボバース上級講習会 修了
2024年 自費リハビリ施設 脳卒中リハビリパートナーズhaRe;Az施設長に就任
2025年 株式会社i.L入職 NEUROスタジオ千葉の立ち上げ
現在の活動
ニューロスタジオ千葉 施設長
脳卒中患者様への専門的リハビリ提供
療法士向け教育・指導活動
千葉ハンドリングセミナー共同代表

